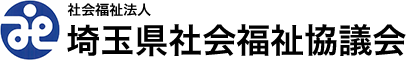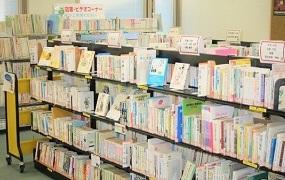県社協のご紹介
- ホーム
- 県社協のご紹介
- 巻頭インタビュー(2025年3月)
巻頭インタビュー(2025年3月)
詩のチカラを信じて ~言葉を通じた若者支援~
読む人に新たな世界を感じさせる詩をつくりあげ、多くの人を魅了している向坂くじらさん。詩人としての創作活動とともに、小学生から高校生が対象の学習塾「国語教室ことぱ舎」の運営やフリースクールなどで行う詩の出張授業を通じて、読むこと・書くことの大切さ、詩の面白さや魅力を発信しています。今回は向坂さんの多岐にわたる活動への思いを伺いました。
 Photo:Kikuko Usuyama
Photo:Kikuko Usuyama
詩人
向坂(さきさか) くじらさん
1994年、名古屋市に生まれる。慶応義塾大学文学部卒。埼玉県桶川市の自宅で2022年2月から「国語教室ことぱ舎」を主宰。ギターのクマガイユウヤさんとのユニット「Anti-Trench」朗読担当。フリースクールなどで行う詩の出張授業や、ワークショップを通じて、詩の面白さや言葉の力を伝えている。主著として、詩集『とても小さな理解のための』、エッセイ集『夫婦間における愛の適温』、『犬ではないと言われた犬』、小説『いなくなくならなくならないで』他多数。

詩の出張授業
--詩人として活動するようになったきっかけからお聞かせください。
高校生の頃は小説を書いていましたが、大学生のときに朗読のパフォーマンスという世界があることを知りました。舞台で詩を朗読したり、音楽と合わせて朗読したりするのですが、そこで詩人の方と知り合い、詩を書くようになりました。
詩の面白いところは決まりごとがなく自由であることです。これまでなかったような詩をいかにして生み出すか、いかに今までの詩を裏切ることができるか、常に詩の側から試されているような気がしていて、その感覚がすごく気に入っています。私の場合、分からないこととか承服しがたいことについて考えていくうちに、それが詩という形で出力されてくる気がします。
--国語教室ことぱ舎を始めるきっかけとその内容について教えてください。
私は大学生の頃から国語の家庭教師と、詩人としての詩の講座の仕事をしていましたが、どちらで話していることにも偏りがあるように感じ、学校の勉強と詩を書くことの両方が分離しない形で教育を行いたいと思ったことがきっかけです。
ある課題に対して結論が出るまで考えるには、学習して得る知識も、自ら新しく考える力も、その両方が必要です。クリエイティブなものを書くためにも、もちろん知識が要ります。その知識をどのように自分の中で結び付けていき、どのように定着させていくかが大事です。
国語教室ことぱ舎は、国語を専門とした少人数制の学習塾です。自学自習形式で一人一人が自分の課題に取り組み、私はそれをサポートします。対象は小学校3年生から高校生までで、月火木に行っています。教室では、詩に囚われず、読んだ文章を要約したり、広く文章を書いたりすることで読む力、書く力の習得に力を入れています。
国語が苦手で通っているお子さんが多いですが、逆に書くことが好きで通ってくる子もいます。自分が苦手なところに戻って学び直すことができるので、不登校のお子さんも複数いらっしゃいます。
--詩の出張授業など、詩にまつわるさまざまな活動もされているそうですね。
詩の出張授業は、フリースクールや小学校の授業で行うこともあれば、小学校の先生向けの研修会で行うこともあります。
また、大田区若者サポートセンター フラットおおたで月に1回、詩の講座をやらせてもらっています。フラットおおたは、引きこもりなど、さまざまな困難を抱えた若者のための相談支援や居場所づくりを行っているところです。
毎回いろいろなテーマの詩を持っていき、何について書かれているか、どう書かれているかを話し合い、その後、何かしらのお題、例えば「比喩を使った詩を書いてみてください」や「こどもの頃の自分に戻って詩を書いてみてください」などのお題を出して、詩を書いてもらいます。
作品を創るということよりは、作品を創った後のコミュニケーションを大切にしています。初めは何も話さなかった方が、回を重ねるごとに他の方の作品に対してすごく前向きなリアクションをすることがあります。他の人の作品を読んだり、自分の作品を読んでもらったりした後ですと、その人の内面に触れて親しみを感じ、少しずつお互いの意思や感情を伝え合えるようです。
--出張授業などでのやりがいや心掛けていることはありますか。
話があまり得意でない方が、面白い詩を書かれることがあります。一般的なコミュニケーションで使われる言葉は分かりやすくなめらかになるものですが、そうではなく、何かまだひっかかりがある、何かごつごつした手触りが残る感じの言葉に出会えることがすごく面白いですね。
いろんな言葉を知って、いろんな人と喋れるようになったうえで、うまく共有できないことを言葉にすることができるのはいいことだなと思っていて、その人らしい感性が失われないようにしたいと思いながら日々やっています。
--最後に、困難を抱えた若者と接するうえで大切にしていることを教えてください。
専門職の方と一緒に仕事をさせていただくことが多く、そういった場合、ケアの専門家でない自分にできることはなんだろう、といつも考えます。支援の現場で求められるのは肯定的な言葉掛けであることが多いですが、教えるということはどうしても現状の否定を伴います。その狭間で悩むこともありますが、専門職の方たちの力を借りながら、書く経験を通してであれば「もっと良いところへ行ける」というメッセージも伝えることができるのではないかと思っています。