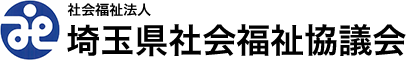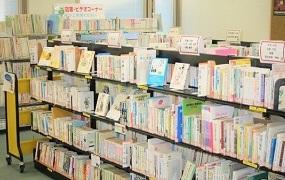県社協のご紹介
- ホーム
- 県社協のご紹介
- 巻頭インタビュー(2025年4月)
巻頭インタビュー(2025年4月)
障害がある人の表現活動が生み出す力 ~社会とつながって、豊かな発達をもたらす~
一人の障害者の支援に行き詰まって模索するなかで表現活動を仕事にするという発想が生まれたと話す宮本恵美さん。表現活動を支えてきた長い経験のなかで培った取り組み方や、障害者アートへの想いを伺いました。

社会福祉法人みぬま福祉会「工房集」管理者、埼玉県障害者芸術文化活動支援センター「アートセンター集」センター長
宮本 恵美(みやもと めぐみ)さん
1991年社会福祉法人みぬま福祉会に入職。2002年「工房集」の立ち上げに関わる。障害のある人の表現活動を仕事と位置づけ、新たな価値を創造することで社会とつなぐサポートをしている。2009年より埼玉県障害者アートフェスティバル実行委員を務め、埼玉県障害者アート企画展の運営に関わる。また2016年より埼玉県障害者芸術文化活動支援センター「アートセンター集」を運営。県内福祉施設職員等と埼玉県障害者アートネットワークTAMAP±〇(タマッププラマイゼロ)を構築し、県内の多彩な表現の魅力を発掘・発信している。

▲TAMAP±〇
利活用などご相談ください

横山 明子さん
自分のペースで穏やかに1日を過ごしながら、大好きな絵を描き続けています
--障害者施設で表現活動を始めた経緯からお話しいただけますか。
みぬま福祉会は、1984年の設立当初から、どんなに重い障害があっても受け入れて一人一人を大切にすることを実践の柱にしてきました。そして働くことは権利だと考え、労働権を保障してきました。
私が入職した頃は、機械油を拭くためのウエス(布)作りや、缶プレスなどが主な仕事でしたが、約30年前に横山明子さんが入所したことがきっかけで、大きく方向転換することになったのです。
横山さんの担当は私だったのですが、こちらが用意した仕事は全て拒絶し、仕事をしてもらおうと繰り返し働きかけても、私との距離は遠のくばかりでした。そこで、ただ「仲良くなろう」と決めて、関わるようにしたところ、絵を描くことがとても好きなことが分かりました。そこで施設のお祭りのポスターに使う絵をお願いすると、すんなり描いてくれたのです。
私は「彼女はこれを仕事にするしかない」と思い、表現活動を仕事にするという発想が生まれました。法人内では反対意見もありましたが、議論を重ねるなかで、労働の定義を「社会につながること」「お金を稼ぐこと」「本人の豊かな発達につながること」と定め、この3つを達成することを目標に取り組んでみようということになったのです。
--表現活動を進めるうえで、職員の皆さんはどのような視点や方法で支援しているのですか。
それまでは仕事のやり方を指導する、指示するといった関わり方でしたが、表現活動では一人一人の得意なこと、好きなことを見つけてそれを仕事にします。職員はその人らしい表現を引き出すための声掛けや、雰囲気づくり、環境設定などを担い、その人のペースで制作を進めていきます。このように関わる中で、少しずつ作品が生まれるようになりました。
2002年に開所した「工房集(しゅう)」は、当時としては珍しく、アトリエ、ギャラリー、ショップ、カフェの機能を持ち、表現活動を社会につなげる役割を果たしています。日常的に場を開放し、展覧会やワークショップを随時開催することで、家族や地域の福祉関係者、住民、アーティスト、美術の専門家などさまざまな人が訪れ、コミュニケーションが生まれる場にもなっています。
ワークショップでは障害のある仲間が講師となって、地域の方たちにアートの楽しさを伝えることもあります。また、外部の方がアトリエを見学する際は、職員のサポートを受けながらも、本人自ら作品を紹介しています。ちなみに当法人は「利用者」という言葉は使わず、ともに時代を生きるという意味で「仲間」という言葉を使っています。
--現在の活動状況を教えてください。
現在は県南を中心に、法人全体で22の事業所を展開していますが、アトリエは13ヶ所あり、約150人の仲間が表現活動に取り組んでいます。絵画だけでなく織物、ステンドグラス、木工など実に多様です。
職員の力だけで表現活動を支えることは難しいため、さまざまな分野の専門家やアーティストなどの力を借りながら作品のクオリティを高め、商品化に取り組んできました。企業とのコラボレーションも進めていて、作品を利活用したノベルティグッズを製作したり、アパレルメーカーと連携して、絵画がプリントされた衣類を商品化したりという例もあります。
作品そのものを販売することもあれば、グッズやアクセサリーに商品化して販売することもあり、いずれにしてもお金を稼ぐことができる活動になっています。
また、作品は海外で開催されるものも含めて、積極的にさまざまな展覧会に出展しています。会場では「感動した」「癒された」といった賞賛の声を数多く聞いており、障害者アートに大きな力があることを実感するとともに、社会とつながることの意義を感じ取りました。
冒頭で紹介した横山さんのお母様は展覧会場で娘の作品を褒めるギャラリーの声を聞いて、嬉し涙をこぼされました。そのことは今でも活動を続ける原動力になっています。
--埼玉県の障害者アートの取り組みは先進的だと言われますが、今後期待することをお聞かせください。
障害者の自立や社会参加の促進、多様性を認め合う社会の実現を目指す手段として、全国に先駆けて2009年から、福祉や美術、教育の関係機関と県が連携して障害者アートの普及を推進してきました。同年には「埼玉県障害者アートフェスティバル」が始まり、私も実行委員会の委員を務めています。また同時に県主体で「表現活動状況調査」が行われ、その調査票をもとに多様な視点を交えて作品を選考し、「障害者アート企画展」を開催していますが、この手法は埼玉県独自のものです。
2016年からは国と県の助成を受けて、障害者アート活動を支援する拠点「アートセンター集」を開設しました。私たちが長年培ってきた経験を活かし、県と連携しながら進めています。「表現活動を始めたいが、時間的な余裕がない」といったさまざまな相談に対応しています。
また、この事業の一環として、県内の福祉施設の職員や他分野の専門家で構成される「埼玉県障害者アートネットワークTAMAP±〇(タマッププラマイゼロ)」を立ち上げました。このネットワークが中心になって展覧会や普及啓発に係る研修会を実施しています。このような活動のなかで私たち職員に支援の眼差しが育まれ、人材育成にもつながっていると手ごたえを感じています。
障害のある仲間はこの表現活動を通して、社会とつながるだけではなく、社会から認められるという経験もできました。自ら作品の魅力を発信している仲間もいます。表現活動は本人の豊かな発達につながり、生きる力を育む素晴らしい活動だと実感しています。