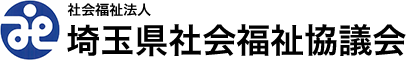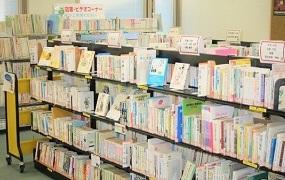県社協のご紹介
- ホーム
- 県社協のご紹介
- 巻頭インタビュー(2025年6月)
巻頭インタビュー(2025年6月)
こども・子育てにやさしい保育施設であるために ~保護者の孤立・不安を解消し、こどもの育ちを支える~
昨年末、こども家庭庁において、令和7年度から3年間の「保育政策の新たな方向性」が取りまとめられました。全ての子育て家庭を支援する取り組みとして、親が働いていなくても保育園に通える「こども誰でも通園制度」(※)が創設されるなど、こどもまんなか社会の実現に向けて保育施設の役割はますます大きくなっています。
今回は、埼玉県保育協議会会長の喜多濃定人さんに現在の保育政策を取り巻く環境と「保育」への思いについて伺いました。

埼玉県保育協議会会長
喜多濃(きたの) 定人(さだと)さん
全国保育協議会常任協議員、関東ブロック保育協議会副会長、埼玉県社会福祉協議会理事の他、数多くの保育関連団体で重責を担う。
また、社会福祉法人光輪会理事長として、「耐える心と乗り越える力」を培う教育・保育を目標に、心身共に健康で心豊かな園児の育成を目指す設立方針のもと、所沢市で幼保連携型認定こども園「なかよしこども園(本部)」「第二なかよしこども園」、和光市で「和光なかよしこども園」を運営。所沢市のこども園には地域子育て支援センターをそれぞれ併設。

--現在の子育て家庭を取り巻く環境の変化や実態、課題などを教えてください。
今、国内では少子化が急速に進んでいます。令和4年度の全国の出生数は約77万人でしたが、5年度は約72万人。埼玉県では、令和4年度43,451人、5年度は42,108人でした。なぜ少子化になるのかを私たちは考えなければなりません。
昨年、園の見学に生後6ヵ月のこどものお母さんが来たのですが、「引っ越してきて1年半、夫以外の人と話したのは初めてです」と言われて非常に驚きました。誰も知り合いがいないので、日中孤立していたのです。その方にはすぐに子育て支援センターに登録して毎日来てくださいとお伝えしました。保護者を孤立させないことが非常に重要なのです。
当法人が運営する子育て支援センターでは、コーヒーメーカー、電子レンジ、マッサージチェアを配置し、くつろげる空間を設けています。その間は職員や来所した人たちみんなでこどもを見守ります。朝起きて夜寝るまで緊張感を持って子育てしているお母さんたちの孤立感・孤独感の解消につながる空間を提供したいと考えています。
--子育てにやさしい地域にするためにはどのようなことが大事なのでしょうか。
近年はこどもが生まれたときに初めてこどもと接する人が増えています。もっとこどもを産み、育てる環境にしていくために、若い世代のうちからこどもと関わることがすごく大事で、中学生、高校生、大学生といった若い世代が当たり前のようにこどもたちと接する環境をつくっていきたいと思っています。
そのために私の園では中学生、高校生、大学生のボランティアをたくさん受け入れて、こどもたちと実際に触れ合いながら過ごしてもらっています。兄弟がいない若者も異年齢児同士の関わり方を知る機会にもなっています。
実際に男女問わず継続的にボランティアにきてくれる若者もいますし、ボランティアが保育士を目指すきっかけになった若者もたくさんいます。また、こどもと関わる仕事は保育士だけではなくて、例えばスーパーなどのサービス業やさまざまな仕事でもこどもと関わる可能性があるので、ボランティアをした経験が社会に出たときに役に立ちます。
地域の中に保育施設があって、小中学校、高校、大学になってもずっと来られる場所、相談できる場所なんだ、さらにはこどもが産まれた時にこどものことで困ったり、何かあれば相談に行ける場所なんだということを認識してもらえるようになるとうれしいですね。
--「こども誰でも通園制度」が始まりまりしたがどのようにお考えですか。
これからの社会環境を考えたときにこの制度は必要であり、とても期待しています。また、少子化がさらに進むと、保育施設は定員割れとなり、経営面が厳しくなります。そのため、お子さんを安心して託せる場所をつくっていくことは、施設側としてもメリットになるはずです。
自治体では実施している保育施設などの名称をホームページなどで広報しますので、保護者はインターネットで登録してこどもを預けることができます。こどもたちは最初は泣いてしまうかもしれませんが、慣れていけば家庭の中だけで育てられるよりも興味や関心の幅が広がるというメリットがあると思います。また、異なる年齢の子と一緒に過ごすことで、社会性、協調性が身に付くといった効果もあります。安心して預かってもらえ、育児の悩みも相談できるので2人目、3人目・・・という気持ちにつながることも期待できるのではないでしょうか。保護者が何か困ったときに相談できる、必要であればどこでも、短い時間でも預かってもらえるという環境をつくっていかなければ少子化は解消されないと思います。
--最後に、「保育」への思いをお聞かせください。
全国的に保育士が不足しており、保育士の採用は難しく、そしてさまざまな事情で辞めてしまうこともあります。職員確保は重要で困難な課題でもありますが、少子化が進む今、社会福祉法人として保育施設を運営する私たちは、一番に子育てに困っている人たちに手を差し伸べなくてはいけないと思っています。例えば園庭を開放する、離乳食の作り方を紹介する、何か相談があったら来てくださいというパンフレットを配る、地域のお祭りなどで保育ブースを出して、保育施設の情報や保育技術を見せるなど、この地域に住めば子育てのことでいろいろ助けてもらえると思えるような地域づくりをしていくことが大事です。
また、育休中にこども誰でも通園制度を利用し、仕事に復帰する際に「この園だったら安心だからこの園に入園させよう」という切れ目のない流れができてくるといいなと思っています。
埼玉県内に住む全ての子育て世代の人たちが安心して埼玉県に住み続けたい、産み育てていきたいと思ってもらえるようにしていくことが大切だと思っています。難しいこともたくさんあると思いますが、埼玉県保育協議会としても、我々保育事業者がちょっと努力すれば、笑顔があふれるような地域になる、そんな取り組みを考えていければいいかなと思います。
※こども誰でも通園制度 保護者の就労の有無に関わらず、生後6ヵ月から3歳未満のこどもが保育施設等に通える制度