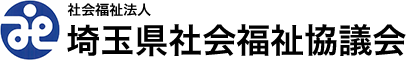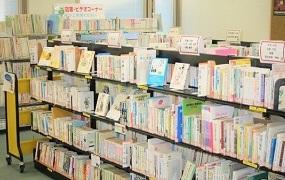県社協のご紹介
- ホーム
- 県社協のご紹介
- 巻頭インタビュー(2023年5月)
巻頭インタビュー(2023年5月)
ヤングケアラーの未来を地域で支えるために~私たちができること、すべきことの実践に向けて~
学生時代からヤングケアラー(※1)に関心を持ち、研究活動を続けながらピアサポートを実践してきた田中悠美子さん。研究や実践から見えてきた、ヤングケアラーが必要とする支援内容や、支援体制づくりのために行政や地域住民に期待することなどについてお話を伺いました。

一般社団法人ケアラーワークス代表理事
田中(たなか)悠美子(ゆみこ)さん
社会福祉学博士、社会福祉士、介護福祉士。日本社会事業大学社会福祉学研究科修了。元立教大学コミュニティ福祉学部助教。研究テーマは、若年認知症者・家族のソーシャルサポートネットワークづくり、ケアラー・ヤングケアラー支援、地域福祉。2012年にボランティアグループ「まりねっこ」を立ち上げ、全国の若年認知症の親と向き合う「子ども世代」への相談支援やピアサポート活動、ネットワークづくり等を行っている。2022年には法人格を取得し、現在に至る。
日本ケアラー連盟理事、埼玉県ヤングケアラー支援推進協議会議長、東京都ヤングケアラー支援検討委員会委員を務め、ヤングケアラー支援に携わっている。

--ヤングケアラー支援に関わるようになったきっかけを教えてください。
私は大学時代に若年認知症の方とそのご家族に出会い、高齢者の認知症とは異なる生活課題を抱えていることを知りました。その家族を支援する家族会の活動に参加する中で、子どもや若者が主たるケアラーとなるケースを目にし、やりたいことが制約され、孤独を抱えていることが分かり、大きな衝撃を受けたのです。
その後、研究活動として取り組み、若いケアラーの声を数多く聞くなかでピアサポートの必要性を感じ、2012年に「まりねっこ」という若年認知症の親と向き合う子ども世代の集いを立ち上げました。「私もそうだったよ」と言える人がそばにいて、時には泣いてしまう方の背中をさすったりと、ぬくもりのあるつながりができる場づくりを進めています。
そして、2022年には一般社団の法人格を取得して、「ケアラーワークス」を設立し、若年認知症に限らず、多様な若い世代のケアラーのつどいやLINEコミュニティ「けあバナ」の運営のほか、啓発のためのシンポジウムなどに取り組んでいます。
--ヤングケアラーにはどのような支援が必要だと感じていますか。
もちろん、子どもたちの負担を減らす意味で家事援助サービスなど支援策の充実は当然必要なのですが、それ以前に親の病気を受け入れるまでの葛藤や「なぜ自分だけが」と不満に思う気持ちなどを吐き出す機会をつくって、共感しあうことがとても重要だと感じています。
私はヤングケアラーの支援に、4つの「ソーシャルサポート(社会的な関わりの中で行われる支援)」の概念を当てはめて考えています。「情緒的なサポート」では共感しあい、「情報的サポート」では介護や医療に関する知識を得て、「評価的サポート」では気持ちをありのまま認めつつ本人の状況の評価をし、「手段的サポート」では具体的に問題解決のための資源やサービスを提供する、という4つの支援です。本人の気持ちや状況に応じてこうしたサポートを組み合わせることが、本人や家族に寄り添った支援につながります。
--埼玉県では多様な主体が連携した支援体制づくりを目指し「ヤングケアラー支援推進協議会」を設置しました。
この協議会は行政、教育、福祉、医療、経済など多様な分野の方で構成され、また、子ども食堂、学習支援などを行う民間団体にも加わっていただきました。私は議長として、委員の皆さんが各現場の状況や、日ごろの実践において感じていること、必要だと思うことをたくさん発言でき、物事を共有しやすい場を意識しました。議論を通して、支援にはさまざまな関わり合いや地域特性があることが明らかになりました。
自治体によって、社会資源やマンパワーなどが異なりますので、その特性を生かして、行政、教育、社協、専門職、地域の民間支援団体や企業が連携・協働した支援の仕組みを創り上げていくことが必要だと考えました。多様な主体が連携した市町村地域でのヤングケアラー支援体制づくりは埼玉県特有の支援の形です。その成果としてヤングケアラー支援のためのスタートブックも完成しました。
--埼玉県や市町村の施策についてどのようなことを期待されますか。
埼玉県は2020年、全国に先駆けて「埼玉県ケアラー支援条例」を制定したことから、トップランナーとして多くの自治体から注目されています。さらに「包括的な支援体制づくり」や「重層的支援体制整備事業(※2)」の実施に向けて市町村へ働きかけています。
ヤングケアラー支援は庁内連携が鍵となるなど、「重層的支援体制整備事業」と共通項がありますので、市町村の特性を生かして推進していただければと期待します。
ただ、各市町村で実際に進めていく場合、ヤングケアラーの“ヤング”にこだわってしまうと縦割りにつながって児童の分野で囲ってしまったり、18歳で支援が終わってしまうことになりかねません。20代、30代とケアが続くことも珍しくありませんので“ケアラー”という言葉に視点を置いて、切れ目なく支援してほしいと思います。
--地域福祉の活動者や地域住民への期待もお聞かせください。
近所のおじさん、おばさんと子どもたちの顔の見える関係がとても大切で、日ごろのあいさつを通して子どもの変化に気付くことを期待します。ただしヤングケアラー支援はデリケートな部分があって、簡単に踏み込むことはできません。「心配しているよ」ということを伝えていただいて、場合によっては「専門の機関があるから一緒に行こう」と誘ってください。
また、民生委員・児童委員、子ども食堂などの実践者の皆さんは、気になる子どもの話を聴いて、ありのままを受け止めてあげてください。話を丁寧に聴いていくことで、少しずつ信頼関係が築けると思います。もちろん、問題をご自身で背負い込む必要はなく、「ちょっと気になるな」という段階で行政や社協に相談されるとよいと思います。
--最後に、ケアに関わっている福祉の専門職の皆さんにメッセージをお願いします。
要支援者への対応とともに、その家族にも関心を向けていただき、子どもがどんな役割を担っているか気に留めてください。そして、その子がどんな思いでケアを担っているか、どうしたいのかを知ってほしいのです。
家族のケアを担うことは悪いことではありませんし、「病気の親を支えたい」という気持ちを尊重してほしいのですが、過剰な責任感をもつことで、自分のやりたいことを諦めてしまうこともあります。要はバランスがとれているかが大切です。子どもは自分の人生を考えるゆとりがなくなっているので、「3年後、5年後はどうしたいか」という投げかけが大きな意味をもちます。行きたい学校に進学することや、やりたい仕事に就く夢を諦める必要はなく、いろいろな可能性が開けていることを子どもたちに伝えていただきたいと思います。
※1 ヤングケアラーとは(埼玉県ケアラー支援条例より)
高齢、身体上、精神上の障害又は疾病等により援助を必要とする親族、友人その他の身近な人に対して、無償で介護、看護、日常生活上の世話その他の援助を提供する者(ケアラー)のうち、18歳未満の者
※2 重層的支援体制整備事業とは
地域住民の複雑化・複合化したニーズに対応するため、属性を問わない相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に実施する事業