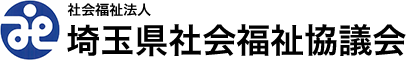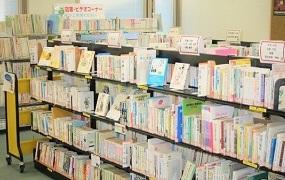県社協のご紹介
- ホーム
- 県社協のご紹介
- 巻頭インタビュー(2023年10月)
巻頭インタビュー(2023年10月)
できてもいいし、できなくてもいい ~あなたのままでいいと言える世の中へ~
次男・美良生(みらい)くんが誕生した後、ダウン症であることが分かり、大きく心が揺らいだという奥山佳恵さん。葛藤や不安の中、美良生くんの愛くるしさや、自身の母親からの愛情を知り、前向きな子育てができるようになったそうです。
今月は、奥山さんご自身とご家族が、どのように向き合い、共に生きてきたのかを伺いました。

俳優・タレント
奥山 佳恵(おくやま よしえ)さん
東京都出身。1990年映画の全国オーディションにてグランプリを射止め、92年主演でスクリーンデビュー。翌年日本アカデミー賞新人俳優賞受賞。以降、ドラマ・バラエティー番組などで活躍する。現在は、ダウン症の次男を迎えての家族の日々などを伝えることでダウン症への理解を深めてほしいと、TVやイベント出演、講演活動なども積極的に行っている。また、著書出版、イラストや水彩画で綴るブログやインスタグラム、WEB連載なども人気を集めている。

在住している藤沢市のオリジナルTシャツを嬉々としておソロで着ている私たち(2023年初夏、奥山さん提供)
--次男の美良生くんがダウン症と分かったときの気持ちからお聞かせください。
次男は生まれてすぐに、心臓に穴が開いている心室中隔欠損症と診断されました。無事手術で根治しましたが、その後、ダウン症であることが分かり、家族それぞれに大きく心が揺らぎました。目に見えないけれど、心に傷を負った状態でした。
初めは、ダウン症の子のことが分からないから不安でこわいと思っていました。でも抱っこしていると本当に可愛い。私は傷を負った心に筋肉をつけて自分の力で立とうと思ったときに、この可愛いという気持ちを大きくする作戦に出ました。まず近所の人に次男のダウン症のことをお伝えしながら、自分に言って聞かせます。最初は自分の言葉に傷つきましたが、家に帰って抱っこをして可愛いパワーをもらって回復することを繰り返しました。次第に相手の顔を見ることができ、言葉も聞けるようになりました。
最後に伝えたのは母でした。いつも笑顔で前向きな母に否定されたらどうしようとなかなか伝えられなかったのです。「一緒に育てていきましょうね」と言われ、嬉しさと安堵で号泣しました。実は母は次男が誕生したその日に障害があるかもしれないと感じて、ずっと心配してくれていたそうです。母が大きな愛で包んでくれていたと知ったときに、次男は可哀そうな子でも不幸な子でもなくて、大事な息子なのだと心から受け入れることができました。私の次男の子育てはここから始まったと思っています。
--地域でダウン症の子育てをして感じたことは何ですか。
28歳で長男を授かったときは周りにママ友はゼロでした。10年経って次男が誕生したときは一緒に子育てをする仲間がいて、ダウン症の情報もあふれていました。障害がある子の親たちはお互いの気持ちが分かるだけに皆でケアしていく体制ができていて、定期的に情報交換をしています。
今思うのは、私は周りの方に恵まれてたくさんの情報を取得できますが、そうでない人も多いのではないかということです。例えばさまざまな支援が受けられる療育手帳にしても、病院の待合室にいた方が教えてくれました。このような大切な情報は口コミではなく、誰でも一律に取得できるようにしてほしいと思っています。
--幼稚園は療育も行う幼稚園でしたが、小学校は普通学級で学んでいますね。
卒園するまでに支援学級か支援学校を選択するのですが、次男は入学前年の夏頃に支援学級への手続きをしました。ところが10月にインクルーシブ教育(※)を推奨している方のお話し会に参加し、そこで初めて、保護者やその子が行きたいと言えば、普通学級も選択することができるということを知りました。そこで知り合った地元・藤沢市の先生方が障害があってもなくても皆で同じ場所にいるべきだと私たちの背中を押してくださいました。
入学前から手を尽くせることは尽くして入学したのですが、大人の心配をよそに子どもたちはすぐに受け入れてくれました。初めは互いの違いに驚きますが、知ってしまえばありのままに包んでしまう。子どもは子どもの中で育つというのは本当なんだと思いました。
うろたえるのは大人ばかりで、大事なことを掴む力は子どもの方が何倍も長けているんですね。
--美良生くんとお友達の様子はいかがですか。
コロナの時期に学童保育に行く日を減らしたところ、「学童に行かないのなら一緒に遊びたい」と次男の同級生が15人くらい我が家にやってきました。
子どもたちは次男と遊ぶためにその場で新ルールを考えるのです。ドッジボールでは、ボールを投げるのが下手な次男はボールを持ったまま相手の陣地に行くことができる、鬼ごっこでは、次男は走るのが遅いので、全員早歩きで、絶対走ってはいけない。かるた遊びの読み手は次男です。次男は言葉が明瞭でないので、次男の言葉がよく聞き取れる子どもが勝つ。
ハンデがあるならどう工夫するのかを皆が考え、皆が本気で遊ぶ。遊びの中での対等を見ることができました。
--美良生くんを育てる中で感じたことをお話しください。
「障害があるからと言って恐れることなかれ」と今は思っています。次男はよく寝てよく笑ってよく食べる、すこぶるいい子です。学校から帰ると自分から宿題などその日の学習をして、明日の支度をしてから自由時間です。
私はちょっとしたことで気持ちが沈んだりすることがありますが、毎日幸せそうにしている次男を見ていると、人は幸せになるために生まれてきたということに気付かされます。
次男の生き方から学んだことは、できてもいいし、できなくてもいい、できなくても悪いことではないということです。できないあなたもあなたのままでいいと言える世の中が誰もが生きやすい世の中だと思います。
--最後に読者へのメッセージをお願いします。
次男がダウン症であることが分かったとき、私の心が整わないとどんな励ましの言葉も情報も受け入れられませんでした。もし、皆さんの周りで障害のある子が生まれたときは、お母さんが立ち上がるまで見守っていただけたらと思います。
私はブログやインスタグラム、講演会などで子どもたちの様子を包み隠さずお伝えしています。それは、私がかつて思っていたダウン症がよく分からなくて不安・こわいというイメージが、もし今、皆さまの心の中にあるのであれば、それを払拭したいと思うからです。
また次男のお友達は、次男がいろいろなことができないことを分かったうえで付き合ってくれています。「できないことがある人もいる」ということを受け入れ、知ってくれている、そんな子どもたちが頼りがいのある大人になってつくる社会を見てみたいなと思っています。
※インクルーシブ教育とは
障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組みのこと。