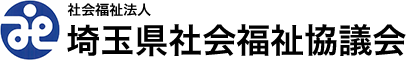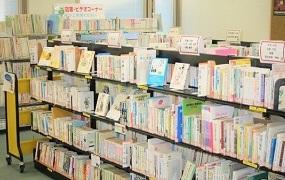県社協のご紹介
- ホーム
- 県社協のご紹介
- 巻頭インタビュー(2024年8月)
巻頭インタビュー(2024年8月)
障害者の人権を守り、共に豊かに暮らすには ~虐待の小さな芽に気付き、それを認める謙虚さを大切に~
「障害者虐待防止法」が施行されて10年余り、障害者の権利擁護の取組が進められてきました。2022年度の厚生労働省(以降、厚労省)調査では、被虐待者数は2021年に続き、過去最多を示しています。そこで今回は長年、記者として障害者虐待を報道する一方、障害者の権利擁護に尽力し、現在は現場で今後の障害者支援のあり方を追求している野澤和弘さんに、虐待防止のために私たちは今、何をすべきか、また障害者支援をこれからどのように考えたらいいかを伺いました。

植草学園大学副学長・教授 毎日新聞客員編集委員
社会福祉法人千楽副理事長
野澤 和弘(のざわ かずひろ)さん

1983年、早稲田大学法学部卒業後、毎日新聞入社。長らく社会部記者として、少年事件、いじめ、ひきこもり、児童虐待、障害者虐待などを報道する。論説委員(社会保障担当)を10年間務めた後に退社し、現職。一般社団法人スローコミュニケーション代表、東京大学「障害者のリアルに迫るゼミ」顧問。上智大学非常勤講師、社会保障審議会障害者部会委員なども務める。障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例の制定(2006年)には研究会座長として関わる。重度の知的障害・自閉症のあるこどもの父。
著書に『弱さを愛せる社会へ~分断の時代を超える「令和の幸福論」』(中央法規)、『わかりやすさの本質』(NHK出版)、他多数。
--障害者虐待防止に取り組むようになったきっかけを教えてください。
私は若い頃は殺人事件などを担当する事件記者でした。三重県や名古屋での勤務を経て、10年目に東京本社へ赴任しました。名古屋で生まれた長男に知的障害があったこともあり、東京に来てからは医療、福祉、教育がフィールドの社会部記者になりました。
1996年、茨城県水戸市の段ボール加工工場で障害者虐待の大きな事件がありました。約30人の知的障害者が雇用され、地域では優良企業とみられていましたが社長による暴力、性的虐待が日常茶飯事でした。
その事件に関わっていた知り合いの弁護士から「記者会見をしても誰も記事にしようとしない、どうなっているんだ」と言われ、毎日新聞社会面で最初に報道しました。
知的障害者の証言だけで第三者の目撃証言も物的証拠もない事件では、知的障害者の証言が最後にひっくり返されて冤罪事件となったことがあり、当時、警察もメディアも慎重に扱っていたのです。私も最初は、「必ず名誉棄損で訴えられる」と上司に反対されましたが、私は障害者の親でもあり、記事にしないのはあり得ないと思い、社内で協力してくれる人たちもいて、大きな記事にしました。それがきっかけです。
次の日から全国から反響が殺到しました。「うちの子もそういう目に遭っています」「施設の職員から虐待がありますが怖くて言えません」という話ばかりでした。メディアも司法も障害者の権利問題を社会問題として見てこなかったのです。
--この事件やその後の障害者虐待防止法の成立過程で感じた当事者や家族の思いなどをお聞かせください。
福祉の世界で少々何かあっても、それは支援する側にいろいろな事情があるのだろう、支援してくれる人を責めたらうちの子の行き場がなくなるという親の心情を私は誰よりも分かります。もちろん目の前で自分の子どもが殴られてそれでいいと本気で思う親はいないわけですが、そう思わなければやっていけない現実があるのです。
この事件以降、国会議員、厚労省の官僚、現場の人たち、親たち、本人たち、そして我々メディアも「障害者虐待防止法」の成立に取り組み、2012年10月に施行されました。その過程では、支援者を責めるとこどもの居場所がなくなるのではと、親の会からも反対意見はありました。
今はみんなが障害者の権利を守ろうとしてくれていますが、法律ができた今でも、虐待はなくなっていないと思っています。
--虐待をなくすためにどのようなことが必要なのでしょうか。
大きな虐待は、最初は些細なところから始まります。小さな虐待、私はグレーゾーンと言っていますが、自分がちょっと支援をミスしてしまったり、相手の思いを無視したりして傷つけてしまい嫌な思いをさせたとか、それはどこにでも絶対あることで、むしろないと言っている方が信用できないと思います。グレーゾーンがあること自体を恐れてはいけない、恐れるとグレーゾーン自体も隠そうとします。グレーゾーンをきちんと認めて、そこから支援とは何なのかを考えようというのが私の考えです。
何が大事かというと、小さなミス、グレーゾーンに気付く感性、それを認められる謙虚さが必要であり、それに気付かない鈍感さと認めない傲慢さが怖いと思います。
--虐待をしてしまう人、それを見て見ぬふりをしてしまう人にはどのような思いがあるのでしょうか。またどうしたら止められますか。
虐待があるのではないかと、みんなうすうす気が付いても、まあいいかと見て見ぬふりをして、心に蓋をしてしまうことはよくあることです。お互いの大変さを分かっているし、自分も指摘されるのではないかと思うので、隠さなければいけないと追い込まれてしまうのです。グレーゾーンのうちにきちんと言葉にして職員間で共有できるようにすることがまず大事だと思います。
自分の失敗は言えても人から指摘されるのは誰でも嫌です。だから私はできるだけ自分から言おうと伝えています。また若い人の気付きを先輩が、「何を言ってるんだ」と抑え込んでしまうことがあります。先輩や上司がつくってきた暗黙のルールなどは簡単に変わらないですからね。でも若い人はそれに染まっていないので、その感性を大事にしなければいけないと思います。
虐待したらとんでもないことになることが分かっているのに何でやってしまうのかというと、周りからサポートされずに追い詰められて虐待するということが多いです。そこでは経営者や上司が働きやすい環境をつくっているかが問われます。
--未来に向かって、どういうことに目を向けたらいいのでしょうか。
私は今、強度行動障害の人たちが地域で豊かな生活ができないか、厚労省の科学研究班の方たちと研究しています。きっかけは、上智大学で私の授業を受講していた女子学生が当法人の施設で働くようになり、30歳の自閉スペクトラム症(ASD)の女性が映画館で映画を見たことがないと言うのを聞いて映画館に連れて行ったことでした。この方は周囲に合わせた行動が難しく話し続けてしまうので我々は心配しましたが、映画が始まる前に彼女が周りの席の人たちに事情を説明すると温かく受け入れてくれたのです。
それから私たちは少しずつそのような試みをしているのですが、迷惑をかけてしまったら、支援者が腹を据えて対処することで、地域での理解者を増やしていっています。
--これからの障害者支援について、読者へのメッセージをお願いします。
認知症や依存症、鬱病の人たちが増加し続けている今、知的障害、精神障害など障害者手帳を持った人だけを支援する時代ではないと思います。支援者の役割は、彼らの沈黙と微笑み、これが暗示するものを読み取ってこれからの社会に何が必要なのかを地域の人たちに伝えていくことです。彼らを生きにくくさせている社会を変えていくという、まさに時代的な課題に現場の最先端で取り組んでいるという働く意味を理解してもらいたいと思います。