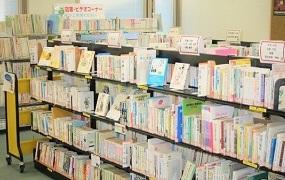福祉の相談窓口
- ホーム
- 福祉の相談窓口
- 運営適正化委員会
運営適正化委員会
※感染症予防のため、以下の対応を行うことがございます
①職員のマスクの着用(マスクの着用は個人の判断となります)
②室内の換気やアクリルパーテーションの利用
③対応の際の適切な距離の確保
※電話相談をご利用ください。
来所による相談も可能ですが、出来るだけ事前にご連絡をお願いいたします。
福祉サービスに対する苦情相談
埼玉県運営適正化委員会とは
※社会福祉法第83条に規定されている機関です。
福祉サービスの苦情について相談を受け付け、解決に向けて助言や苦情に至った状況についての調査、あっせんなどを行います。委員会の委員は、公正性及び多様な事例に対して適正に機能を発揮するために、「社会福祉に関し学識経験を有する者」、「法律に関し学識経験を有する者」、「医療に関し学識経験を有する者」の各分野から選任されています。
社会福祉法第82条において社会福祉事業の経営者は提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならないとされています。事業所には、苦情受付担当者、苦情解決責任者、第三者委員等の相談窓口が設置されています。まずは事業所の相談窓口にご相談下さい。
利用者と事業者との話し合いで解決ができなかったり、事業所に伝えにくい苦情や不満などについて、埼玉県運営適正化員会が相談を受け、助言、苦情となった状況の調査、あっせんなどを行い、解決に向けて支援します。相談は無料です。秘密は守ります。
相談できるサービスの範囲
○社会福祉法に規定する社会福祉事業(第1種、第2種社会福祉事業)が対象です。医療や制度(生活保護等)に関しては対象外です。
○類似の福祉サービスについては委員会の判断により対応することになります。
介護保険サービスに関する苦情は、市町村の介護保険担当課(保険者)、埼玉県国民健康保険団体連合会(電話:048-824-2568)において受け付けています。
相談できる方
福祉サービスを利用されている本人、家族、代理人、民生委員・児童委員、その施設の職員等で利用者の状況や提供されている福祉サービスの内容を良く知っている方です。
例えば、このようなお困りごとはありませんか
○契約時の説明と実際の状況が異なっている。
○職員の言葉遣いや態度が悪いので注意したいけれど言いにくい・・・
○施設内で転倒し、骨折をした。事故の経過を聞いたけれど、説明があいまいで納得できない・・・
○入所の際に寄附金を支払った。その後も何かと請求が来るのだが、支払う必要はあるのだろうか。
○施設に苦情を申し出たが改善が見られない。
相談方法
電話、手紙、来所などで相談してください。
来所の場合は電話で御連絡ください。
※匿名の相談も受け付けていますが内容によっては具体的な対応が出来ない場合があります。
不明な点はお気軽にお問合せください。相談は無料です。秘密は守ります。
相談専用電話番号 048-822-1243
FAX番号 048-822-1406
受付時間 月曜~金曜日
9:00~16:00
(土曜・日曜・祝日・年末年始は休みです)
住 所 〒330-8529
さいたま市浦和区針ヶ谷4-2-65
彩の国すこやかプラザ 1階
埼玉県運営適正化委員会
案内図
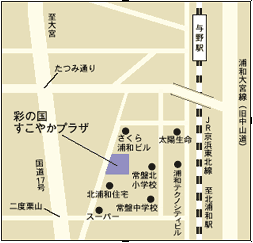
埼玉県運営適正化委員会での相談の流れ
※ご相談の内容や本人の意向によって対応順序が異なる場合もあります。
1 苦情受付(電話・手紙・FAX・来所等)
運営適正化委員会事務局の職員が、苦情の内容や意向をお伺いします。
匿名の相談も受け付けています。具体的な対応を希望される場合は、事業所名、相談者名等をお伺いすることもあります。
※お話を伺った範囲で申出人への助言を行います。
※虐待や法令違反などの重大な行為がなされたことが明らかな場合には速やかに県知事への通知や虐待通報、通告等を行います。
2 委員会開催
苦情の内容や意向をふまえて解決のための方法や手順を委員会で協議します。
解決方法としては、以下の方法が多く用いられます。
①苦情申出人からの苦情内容について、申出人の了解を得た上で事業者に伝達し、事業者から申出人にわかりやすく説明していただくよう依頼します。(当事者同士の話し合い)
②必要がある場合、苦情に至った状況を確認するための事情調査を実施します。
③明らかな権利侵害、虐待、法令違反など重大な行為の場合は速やかに県知事に通知します。
3 事情調査(聞きとり調査、現地調査)
委員会の委員または事務局職員が、申出人・事業者双方の了解を得て、苦情内容についての確認や事業者の考え方、今後の対応等をお伺いします。
4 解決方法の協議
事情調査の結果に基づき、申出人に対する助言や、事業者に対する申入れの必要性について検討します。状況に応じて申出人・事業者双方に対し、あっせんについての説明を行います。
5 あっせん
申出人、事業者双方の同意が得られ、希望があった場合、あっせんを行います。
参考資料
社会福祉事業経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針  (125KB)
(125KB)
第三者委員の役割と活動  (257KB)
(257KB)
福祉サービス事業者の円滑な苦情対応のために
社会福祉事業の経営者は、利用者からの苦情に対し、適切な解決に努めなければならないとされています。福祉サービス事業者が利用者からの苦情に適切に対応し、解決の支援ができるよう「福祉サービス事業者のための苦情解決ハンドブック」を作成しました。
福祉サービス事業者だけではなく、利用される方にも参考になるように作成しました。
ぜひ、ご活用ください。
苦情解決ハンドブック  (5780KB)
(5780KB)
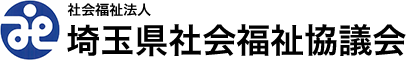
 (45KB)
(45KB)