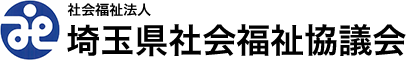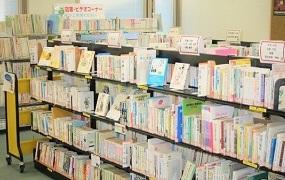県社協のご紹介
- ホーム
- 県社協のご紹介
- 巻頭インタビュー(2025年2月)
巻頭インタビュー(2025年2月)
認知症になっても地域で暮らすために 〜本人が力を発揮できる居場所づくり〜
認知症になっても安心して暮らせる社会の実現を目指して活動する「認知症の人と家族の会」(以下、家族の会)。本部副代表理事・埼玉県支部代表を務める花俣ふみ代さんに、会の取り組みや、当事者の方が地域で暮らすために必要なことについて伺いました。

公益社団法人 認知症の人と家族の会
本部副代表理事・埼玉県支部代表
花俣 ふみ代(はなまた ふみよ)さん
介護福祉士。介護支援専門員。1991年〜1998年姑の在宅介護。1998年家族の会の世話人に。1998年〜2003年、実母を遠距離介護。2004年ヘルパーとして訪問介護事業所で従事。2017年より現職。株式会社福祉の街顧問。厚生労働省社会保障審議会介護保険部会委員。監修した書籍に『認知症になった家族との暮らし方』(ナツメ社)

つどいの様子
--「家族の会」の支部活動に参加された経緯をお話いただけますか。
きっかけは姑と実母の介護をしたことです。まず姑の在宅介護を8年近く担い、1998年に看取りました。「この経験を活かしたい」と考えていたときに、お世話になっていた訪問看護師さんから「家族の会が世話人を探しているのですが、お願いできますか」と、声を掛けていただいたので、98年から活動に参加しました。
姑の看取りと前後して、母の遠距離介護が始まり、さいたま市から京都まで毎月のように通うことになりました。ただ、距離が離れていると、介護の一部しか担うことができず、家族としては後ろめたさを感じてしまうものです。しかし家族の会の活動に参加して母と同じ認知症の方のために役立っていると思うことで、その後ろめたさがいくらか解消され、遠距離介護とともに家族の会の活動も並行して取り組みました。
母が亡くなった後は、ヘルパーの資格を取得して訪問介護事業所で働きました。認知症の方などを介護するなかで、たくさんのことを学び、10年以上続けました。サービスを提供する側と受ける側の両方を体験できたことは、家族の会の活動にも活かされています。
--家族の会支部の活動内容を教えてください。
私たちはつどい、電話相談、会報の発行を活動の3本柱にしています。つどいは、認知症の人を介護する家族や専門職が集まって、日常の悩みなどを話し合う居場所です。県内各地で定期的に開催していて、本人が参加できるつどいもあります。
電話相談は介護経験のある世話人が、介護に悩んでいる方からの相談を受けて、一緒に考えます。週5回実施していて、相談件数は増加傾向にあります。会報については、本部が月刊で「ぽ〜れぽ〜れ」を、支部では「ふれあい」という会報を隔月で発行し、会員の介護体験記、身近なニュースなどを掲載しています。
また、埼玉県・さいたま市の委託を受けて若年性認知症サポートセンターを開設しています。専門資格と経験を有したコーディネーターが、仕事のこと、制度のことなどについて相談に応じており、本人カフェも開催しています。
--家族の会の活動ではピアサポート(※1)を大事にされていますね。
ピアサポートはエンパワメント(※2)につながると考えています。例えば家族は専門職からのアドバイスを素直に受け入れられないことが多いのですが、相手が自分と同じように介護で大変な思いをした人だと思うと、心の扉がすっと開いて、素直に言葉を聞くことができます。初めてつどいに来た方が、これまで誰にも言えなかった大変さやつらさを吐露することができて、思わず泣き出してしまう光景もよく目にします。
そして、つどいへの参加を重ねるたびに、どんどん表情が和らいでいくのです。そのような様子を見ると、家族の会にはとても大切な役割があるのだと実感します。
--認知症の人が地域で生きていくために必要なことは何でしょうか。
2024年12月、認知症施策推進基本計画(以下、基本計画)が閣議決定されましたが、この計画のキーワードは「新しい認知症観」です。これは認知症になったら何もできなくなるのではなく、住み慣れた地域で希望を持って自分らしく暮らし続けられるという考え方のことです。
認知症はコミュニケーション障害ですから、自分の思いを言葉に乗せて相手に伝えることが難しくなりますが、家族等は介護が長期にわたると本人の想いを推し量ることができるようになります。これまでは「何も分からなくなってしまうので、外出は難しい」と考えて閉じこもりがちの生活をしている方が多かったと思いますが、これからは認知症になっても悲観することはありません。
国が定めた基本計画では、誤解や偏見を解消するために、当事者が自分の思いを発信する希望大使の取り組みや、本人ミーティング、本人交流会などの施策を打ち出してきました。一方、家族の会は40年以上前から「認知症になっても安心して暮らせる社会の実現」を目指して活動を続けてきました。
地域の理解が広がれば、認知症の方も地域のなかで活動できるようになると思います。例えば認知症の方が、「地域のこどもたちの役に立ちたい」と、子育て支援に参加するといった活動はすでに始まっていますし、社会への参画を通した本人の役割は地域のなかにたくさんあると思います。
認知症の人が地域で生きていくために必要なものは居場所です。行くことができる場所、自分の持っている力を活かせる場所、そんな居場所づくりを、地域づくりにまで広げていくことが求められると思います。
--最後に、認知症の支援をはじめ、福祉活動に携わっている方に向けて、メッセージをお願いします。
居場所づくりをはじめ、何か活動をスタートしたら、長く続けることが大切です。私はこれまでの経験を通して、続けるための要素は楽しさだと考えています。自分が楽しくなければ、相手も楽しいと思わないし、楽しければ次の開催に向けて意欲が湧き、相手もまた参加したいと思うはずです。楽しいという要素を大切にすると、自然と活動の継続につながるのではないでしょうか。
※1 ピアサポート・・・同じような悩みを持つ人たち同士で支え合う活動のこと。
※2 エンパワメント・・・人が持っている本来の力や可能性を引き出すこと。