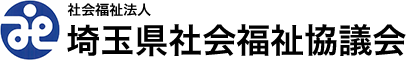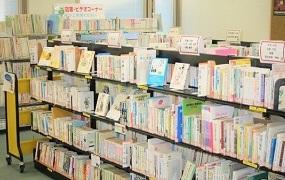県社協のご紹介
- ホーム
- 県社協のご紹介
- 巻頭インタビュー(2025年7月)
巻頭インタビュー(2025年7月)
生きることに向き合う ~私が殺そうとした身体が私を一生懸命生かしてくれた~
幼少期から生きづらさを感じ、小学校高学年の頃からは死にたいと思うようになった豆塚エリさん。16歳の時、さまざまな状況が絡み合い、家庭にも学校にも居場所がなく、自分には生きている価値がないと思い詰め、飛び降り自殺を図りました。頚椎損傷により車いす生活になりましたが、紆余曲折を経て、現在では講演会などで自らの経験を真摯に語り、こどもの自殺を防ぐ活動を行っています。今回は豆塚さんの「生きること」への心の変化について伺いました。

詩人・エッセイスト
豆塚(まめつか) エリ(えり)さん
1993年愛媛県に生まれる。16歳の時自宅アパート3階から飛び降り自殺を図り、頸椎損傷により車いす生活となる。高校復学は叶わず、18歳で高卒認定試験に合格。大分県別府市にて自立し、2022年に自伝的エッセイ『しにたい気持ちが消えるまで』(三栄)を出版。現在は詩や短歌、短編小説などを発表する一方、自身の経験を発信することによるこどもの自殺防止の取り組みや、障害や病気で働けない人へ「もくもくライタースクール」での就労支援など幅広い活動を行っている。

--どのようなことに生きづらさを感じられたのでしょうか。
私の母は韓国人で、私が生まれる前に日本人の父と離婚し、私が3歳の時に再婚しましたが、両親は小学校に入る頃から不仲になりました。
私は鍵っ子で母を支える娘という構図にあったかなと思います。義父は母より年齢が20歳近く上であり、教師であったためしつけに厳しく、両親からの体罰は当たり前にありました。私は義父が苦手で、義父と遭遇しないよう部屋に籠っていました。
そんな家庭環境で育ったこともあり、学校でも人間関係の構築が上手な方ではなかったのですが、勉強はできたので、生徒会やクラブ活動を頑張り、自分なりに居場所を探そうとしました。しかし、学校にも家庭にも居場所がなく、小学校高学年の頃には、消えてしまいたい、死んでしまいたいと思うようになり、中学生になってリストカットをするようになりました。自傷行為をすることで気持ちがホッとする自分と、恥ずかしく思う自分との間で葛藤がありました。
そうした中で、心のよりどころとなっていたのは、本を読むことでした。物語の中の主人公に自分を重ねて、空想を膨らませ自分の世界に入っていました。本を開くといつでもまだ見ぬ世界に入り込むことができました。
--自殺未遂を起こす直前はどのような状況でしたか。
食べる、寝るという基本的なことに罪悪感がありました。お金がないので、食べてなくなるものにお金を掛けることを悪いことと感じるようになりました。また、それまでは朝6時頃には起きて登校していましたが、飛び降りる数日前から起きられなくなり、そのことを母から怒られて、私にはやはり居場所がないのだと感じました。
生きていくのに大切なのは自己肯定感(※1)と自己有用感(※2)と聞きます。私には自己肯定感はないけれど、自己有用感はあると考えていて、それが心の支えになっていました。しかし、この時期はいろいろなことの板挟みになって、自己有用感も失い、自分は生きている価値がないと思うようになりました。一般的に自殺の原因は複雑で、その状況を紐解けないほど健康状態が悪くなって精神疾患を発症すると聞きますが、今思うと、私は鬱になっていたと思います。
死にたい、消えたいと毎日のように思っていたのが最後の最後にぷつんと糸が切れた、そういう感覚に近かったかなと思います。
--生きることに対して、どのような心の変化がありましたか。
気持ちが変わっていったきっかけは、治療過程の痛みから、自分が殺そうとした身体が自分のために一生懸命生きようとしているのを感じたことです。支えてくれる人がいないと思っていた自分を、唯一生かそうとしている自分の身体の存在に気づいたことで、生きることを肯定的に捉えることができるようになりました。
また、病院の医師や看護師さんたちとの関わりも大きかったです。ずっと自分のことは自分でやりなさいと言われ続けてきたので、人に頼ることは悪いことだと思っていました。しかし、身体が不自由になり、病院では何をするにもお願いをするしかありません。すごく親切にしてもらい、何もできなくても生きていていいのだと思えるようになりました。
また、病院は認知症や寝たきりの方、脳挫傷により発語が難しい方など、多様な方を同じ「患者」としている、すごく不思議な空間で、人が生きるということはどういうことかを考えるきっかけになりました。
その後、別府で一人暮らしを始めました。近くに小さな喫茶店があり、そこで本が好きなマスターと本の話をするのが大好きでした。マスターはいろいろ身の上話を聞いてくれた後に「人生っていうのは辛いこと半分、楽しいこと半分、帳尻が合うものなんだ。君はもう充分辛いことばっかりの人生を生きてきたんだから、これからは楽しいことしか起こらないから安心して生きなさい」といつも言ってくれました。その言葉に救われました。
--ご自身の経験を語る活動では、何を大切にしていますか。
こどもの自殺は年々増えています。自分と同じような境遇のこどもをなくしたいというのが一番大きなところです。最初の頃は個人的なことを話すのは恥ずかしいことではないかと思っていましたが、「個人的なことは社会的なこと」という言葉に出会い、それがすごく胸に響き、少しずつ語るようになりました。
26歳の時にSNSでカミングアウトしたところ、多くの励ましの言葉や、自分もそうだったという声も届きました。そうした経験から、自分のことを正直に語ることが何より重要だと思うようになりました。自殺未遂・障害当事者として、講演会では「しにたい気持ち」とどのように向き合い続けているのかをストレートに話をしています。いかに生きる希望を取り戻したのかを伝え続けていきたいです。やればやるほど自分の気持ちが整理できるので、自分のことを自分の言葉で語ることを一番大切にしていきたいと思っています。
--生きづらさを感じている人へどのような声掛けをしたらいいのでしょうか。
本当に難しいことだと思います。自殺未遂をする前後の自分を思い返してみても、死にたい人には言葉は無力だなと思います。言葉を紡いでいる私がそういうことを言うのは無責任な感じはしますが、多分言葉ではなく、その場の空気とか、声の掛け方とか、大事なのは言葉というところを超えることなんだろうと思っています。本当に関わり続けること、あなたのそばにいるんだよということを、何かしら伝えていくしかないかなと思います。
※1 自己肯定感 自分自身に満足している、自分にはよいところがあるなど、自分の自己に対する肯定的な評価のこと
※2 自己有用感 人の役に立った、人から感謝されたなど、自分と他者(集団や社会)との関係を自他共に肯定的に受け入れられることで生まれる、自己に対する肯定的な評価のこと