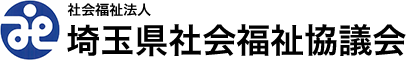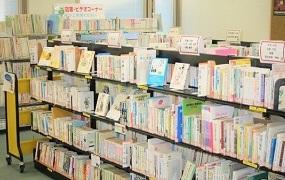県社協のご紹介
- ホーム
- 県社協のご紹介
- 巻頭インタビュー(2024年10月)
巻頭インタビュー(2024年10月)
何でも面白がることが出発点! そこから新しい世界が広がる ~世界最高齢のアプリ開発者~
定年後にパソコンの面白さに目覚め、80代でスマートフォンのゲームアプリを開発された若宮正子さん。Apple社のCEO(※1)からは「世界最高齢のアプリ開発者」と紹介されました。「人生100年時代構想会議」など、政府主催のさまざまな会議のメンバーとしても活躍されています。年を重ねても、次々と新たなことに取り組む秘訣を伺いました。

デジタルクリエーター、ICTエバンジェリスト
若宮 正子(わかみや まさこ)さん
1935年東京都生まれ。東京教育大学附属高等学校(現・筑波大学附属高等学校)卒業後、三菱銀行(現・三菱UFJ銀行)へ勤務。定年後にパソコンスキルを独自習得し、シニア世代へのデジタル機器普及活動に尽力している。
2016年からアプリ開発に着手し、スマートフォンのゲームアプリ「hinadan(ヒナダン)」を配信。米国Apple社による世界開発者会議「WWDC 2017」に特別招待される。
内閣府主催「人生100年時代構想会議」の最年長有識者メンバーにも選ばれた。
※エバンジェリスト・・・IT業界の新しい職種やその役割を担う専門人材のこと。

表計算ソフト「Excel」の罫線やセルの塗りつぶしを使って作る「エクセルアート」も若宮さんが考案。自身がデザインしたブラウスを着用されています。
--高校を卒業してから定年まで大手銀行に勤める中、当時は珍しかった女性の管理職に就任されました。
私は手先が不器用なためにお札を数えるのが苦手で、そろばんも得意ではありませんでした。しかし機械化、デジタル化が進んでいく中で、会社側が行員に求める能力も変わっていきました。
私は新しいアイデアを考えるのが好きで、業務改善計画などを次々と書いて提出したことが評価され、企画開発の部署に転属になりました。当時は女性が昇進試験を受けることは珍しかったのですが、女性でも受験できると知って、それならと勉強し、管理職の端くれになることができました。
--定年後にパソコンスキルを独自に習得されたり、プログラミングに取り組んだり、年齢に関係なく新しいことにチャレンジされていますね。
私はIT(※2)に限らず、新しいことに取り組むときはいつも「面白そうだからやってみよう」という気持ちからスタートします。決して「チャレンジしよう」という思いからではありません。昔から好奇心が旺盛で、なんでも面白がる性格でした。ITもその面白さに惹かれて取り組んだのです。
また、勉強するときは、分厚い入門書を買って1ページ目から読み込むタイプではなく、興味を惹かれることから始めます。タブレットパソコンを初めて購入したときも、「まず、お琴のアプリで『さくらさくら』を弾いてみたい」と思い、そこからいろいろなことを覚えていきました。
--シニア世代の交流サイト「メロウ倶楽部」の設立に発起人として参加し、現在も副会長を務められています。どのようなサイトなのですか。
端的に言えばインターネット上に展開している老人クラブです。1999年に設立して以来、誰もが本音を言える貴重な場として続いています。
例えば「医者から余命3カ月と言われた」といった書き込みもあります。こうした深刻な事柄は直接、顔を合わせる集まりでは言えないことですが、コメントする側も「限りある人生をどう生きるか」を真剣に考えます。私自身も、この交流サイトを通して何人かの先輩とお別れした経験から、さまざまなことを学ばせていただきました。
ネット上の付き合いは冷たいというイメージがあるかもしれませんが、そうとは言い切れないと感じています。何より寝たきりになっても、交流を続けることができるのはすばらしいことです。対面とネット上の交流を、両方とも大事にしていきたいと思っています。
--若宮さんがアプリを開発された経緯についてお話いただけますか。
スマートフォンを使うようになったとき、高齢者が楽しめるゲームがほとんどなかったので、若い人に作ってほしいとお願いしました。すると、「高齢者向けと言われても、よく分からないので、ご自分で作ってみたら」と言われ「それも面白そうね」と思って、プログラミングを勉強することにしました。
私が作った「hinadan(ヒナダン)」というアプリは、ひな壇にひな人形を正しく配置していくゲームで、スピードを競うのではなく、知識を競うものです。高齢者がお孫さんや若者と一緒に遊びながら、「五人ばやし」の並べ方などを教えることができるので、世代を超えた交流の機会になればと考えました。
アプリ完成後、アメリカのApple社から「CEOがあなたに会いたがっている」というメールが届きました。友人は「きっと詐欺メールよ」と忠告してくれたのですが、実はApple社が開催している、開発者向けイベントへの招待だったのです。CEOのティム・クック氏ともお話することができました。
--高齢者の中にはITに苦手意識があったり、拒絶反応を示したりする方も多いのですが、どのように対応していけばよいでしょうか。
先日訪れたレストランは、メニューを携帯で読み取って注文するシステムでした。少子高齢化が進んで人手不足が深刻化する中、IT化を推進していかないと社会が回らない状況になっています。
高齢者であっても、日常生活の中で、ITを使わざるを得ない場面がこれから増えてくるでしょう。
デジタル先進国として知られるデンマークは生涯学習が充実している国としても有名で、誰もがITについて勉強できる環境が整っています。
日本にも生涯学習の仕組みはありますが、その多くが文系の講座です。テクノロジーの面白さなどを伝える理系の講座がもっと増えるといいですね。楽しみながらITを学べる環境が整ってくることを願っています。
--最後に、本誌の読者に向けてメッセージをいただけますか。
何か大きなアクシデントに見舞われたとき、人は文句を言ったり、悲嘆にくれたりするものですが、それで事態は好転しませんよね。そんなときでも、私は自分が置かれた立場を面白がることにしています。日本では不謹慎だと非難されるかもしれませんが・・・。私はこどもの頃に大やけどをして救急搬送されたときも「めったに救急車に乗れないので、救急車の内部がどうなっているか観察しておこう」と、きょろきょろしていました。
皆さんも日々の生活のなかで、面白いことをたくさん見つけてください。例えばAI(人工知能)に話しかけてみるなど、遊ぶのも面白いですよ。そのような遊びから、ITに興味を持つ方が増えていくことを期待します。
※1 CEO・・・最高経営責任者の意味
※2 IT・・・・・・パソコンやインターネットなど情報技術の意味