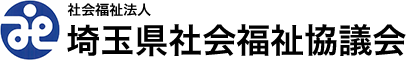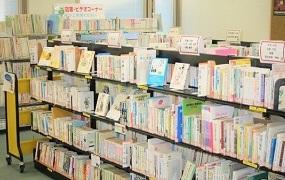県社協のご紹介
- ホーム
- 県社協のご紹介
- 巻頭インタビュー(2025年10月)
巻頭インタビュー(2025年10月)
尊厳のある本人らしい生活を継続するために 〜成年後見制度の利用促進〜
「成年後見制度利用促進法が施行されてから10年目を迎え、制度の理解も広がってきました。今回は制度の利用促進に長年取り組まれてきた司法書士の柴由之さんに、成年後見制度の現状や課題などについて伺いました。
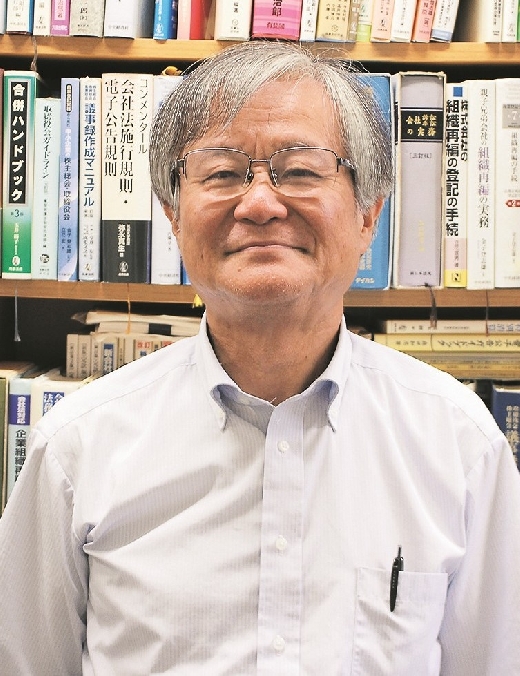
埼玉司法書士会 名誉会長
柴(しば) 由之(よしゆき)さん
1954年生まれ、熊谷市出身。熊谷高校、早稲田大学法学部卒。1993年司法書士登録し個人事務所を開業。2009年(公社)成年後見センター・リーガルサポート埼玉支部長(3期)。2005年埼玉司法書士会理事、2015年5月から2019年5月副会長(2期)、2019年5月から2025年5月会長(3期)。
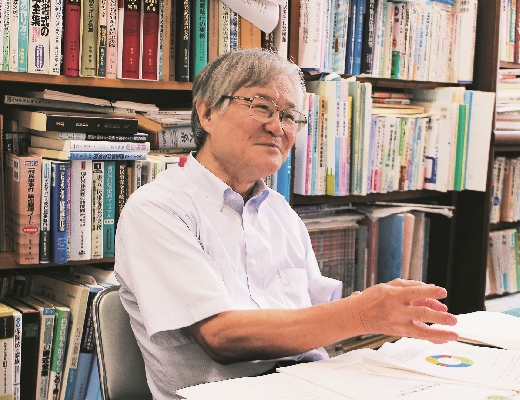
--成年後見制度が施行されて今年で25年になりますが、制度の現状について、どのように捉えていますか。
当初と比較して親族の関与が大きく低下していると感じます。例えば制度が開始した平成12年には被後見人のこどもや配偶者、兄弟姉妹などの親族が、成年後見人等に選任されたケースが全体の90%以上を占めていました。ところがその割合は年々低下し、昨年は17・1%でした。成年後見人等の候補者になることを希望した親族は21・3%でしたので、そもそも希望する親族が少なくなっていることが分かります。
また、申立人の割合を見ても平成12年には90%以上が親族で、市区町村長は0・5%でしたが、親族の申し立てが減少した結果、昨年は市区町村長の申し立てが23・9%でした。
被後見人のことを一番良く知っているのはこどもや配偶者ですので、私は親族が後見人になることが原則と考えてきました。しかし、頼れる親族がいない一人暮らしの高齢者が増えていることや、また近くにこどもがいたとしても、面倒なことは専門職を頼るという流れに変わってきたことで、「成年後見の社会化」が進んできたという実感をもっています。
--成年後見制度に関して柴さんはどのようなことに取り組まれてきたのでしょうか。
まず平成11年に設立した(公社)成年後見センター・リーガルサポートには最初から関わっていて、埼玉支部の副支部長、支部長を務めました。リーガル・サポートは、司法書士を正会員とする全国組織で、裁判所が成年後見人等を選任する際、一定の研修を履修した候補者を推薦する役割などを担っています。
その一方で埼玉司法書士会の副会長、会長も務めました。こちらは成年後見に関する相談を行っているほか、利用促進のための出前講座なども実施しています。司法書士による後見人のなり手不足は司法書士会の課題でもあります。
また、「成年後見制度利用促進基本計画」を県内で円滑に実施することを目的として、平成30年に弁護士、司法書士、社会福祉士と連携して「埼玉県三士会協議会」(以下、三士会協議会)を立ち上げました。私が所属する熊谷支部は令和元年にいち早く三士が集って意見交換会を開催しました。その中でこの制度の利用を促進する目的について、今必要な人に行き渡っていない状況を変えていくためであり、「必要な人が利用できる」がキーワードだと再確認しました。この目的は現在も変わっていないと思います。
--成年後見制度の利用促進の要となる、中核機関の整備について、考えをお聞かせください。
中核機関は権利擁護が必要な人を支えるため、相談に応じたり、地域の関係者と話し合ったり、その人にとって必要な支援につなげる役割を担う「地域連携ネットワーク」となります。この機関は、新規に立ち上げるのではなく、市の担当者、社協、専門職、民生委員・児童委員などが集まる既存の権利擁護や福祉関連の協議体に、機能を付け加えていく形で整備していくことも一つの方法だと思います。これらの関係者が連携できる場を設けて問題意識を共有し、「後見が必要な人を発見し、適切に支援に結びつける仕組み」をつくる。そこまでできれば中核機関だといえます。
役割として広報、相談、利用促進、後見人支援の4つの機能を持つとされていますが、最低限、広報と相談機能は必要です。また支援が必要な人が増加している一方で、支援する人材は不足しているので、地域で担い手を養成する取り組みも期待したいところです。
--市民後見人(※1)や法人後見(※2)など担い手の確保・活躍支援にあたり、必要なことについてお話しください。
市民後見人になるためには、まず養成研修を受講した後、社協の法人後見等における支援員として、後見業務などの経験を積んでから初めて後見人名簿に登載されるので、選任までに4、5年かかってしまいます。時間がかかりすぎることが選任が進まない大きな要因ではないでしょうか。
期間を短縮するための方策として、専門職が財産管理を担い、市民後見人が身上監護を担う「共同受任方式」の導入も考えられます。私自身、多くの方の後見人を務めていますが、遠方の方もいるために頻繁に訪問することは難しい状況です。近隣の市民後見人の方が定期的に訪問していただければ、ご本人のためにもなりますし、我々にとってもメリットがあります。
一方で、住民にとって身近な社協による法人後見が広がることも大切です。どこの社協も後見業務に人手を割くことが難しい状況だと承知していますが、業務を行う上で困りごとがあれば地域の専門職に相談してください。近くに専門職がいない場合、三士会協議会でも相談を受け付けます。多くの社協が法人後見に取り組まれ、県内のどこにいても必要な支援を受けられる体制が整備されることを期待しています。
--現在、国において制度を見直す検討がされていますが、どのようにお考えですか。
見直しについては法務省の法制審議会が6月、中間試案をまとめました。例えば現行の制度では利用を開始すると本人が亡くなるまで止めることができませんが、申立ての目的である不動産売買などの法的な支援が終わった時点で止めることができる案が検討されています。
途中で制度の利用を止めた場合には、預金の管理などの支援を行う受け皿をどうするかが課題となりますが、社協の日常生活自立支援事業や地域の福祉的な支援を活用するなど、司法と福祉の連携によりご本人を支えていくことが求められてくるのではないかと考えています。
※1 市民後見人 弁護士や司法書士などの資格をもたない、親族以外の市民による成年後見人等であり、市町村等の支援をうけて後見業務を適正に担う
※2 法人後見 社会福祉法人や社団法人、NPO法人などの法人が成年後見人等になり、親族等が個人で成年後見人等に就任した場合と同様に、判断能力が不十分な人の保護・支援を行うこと