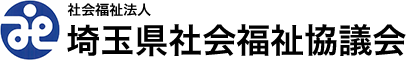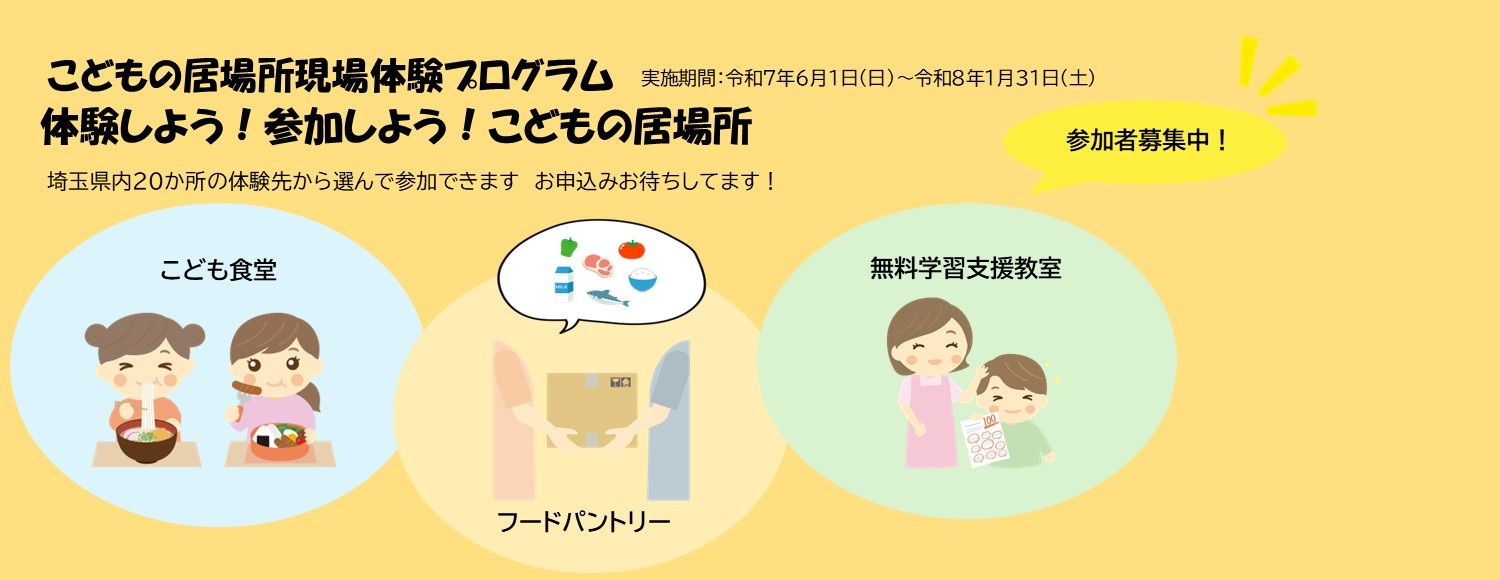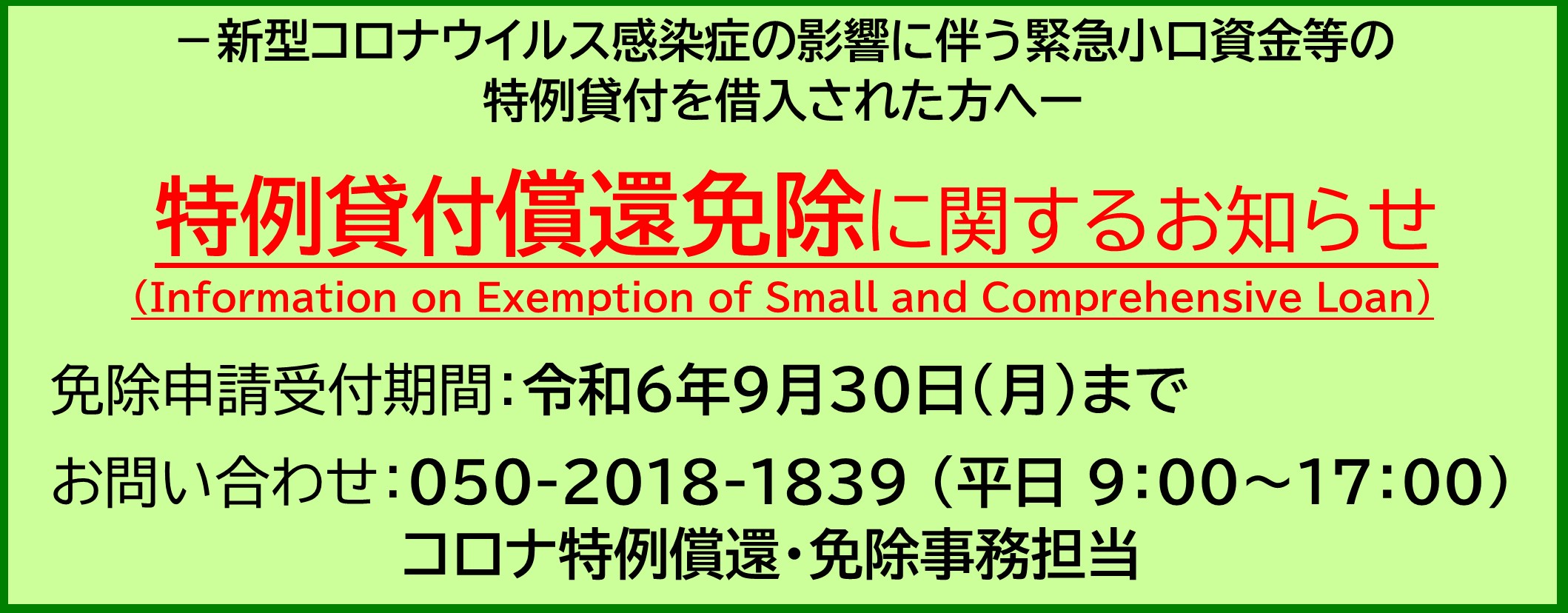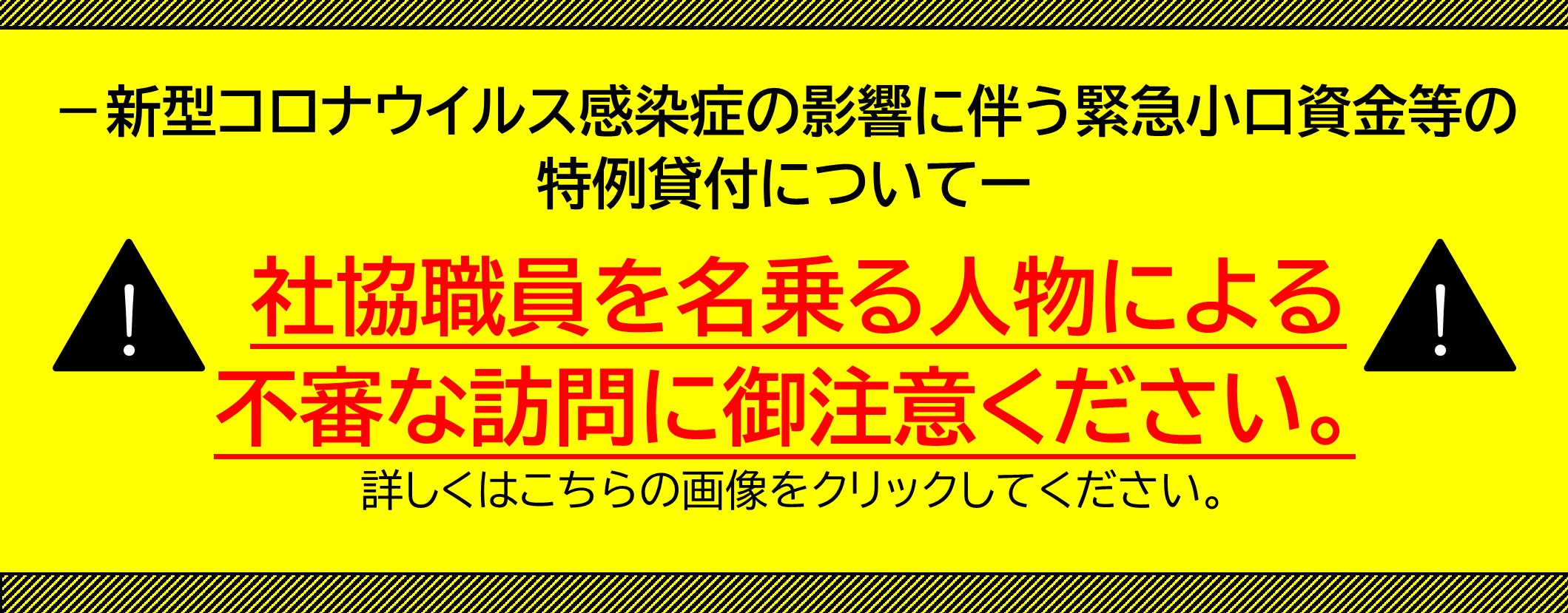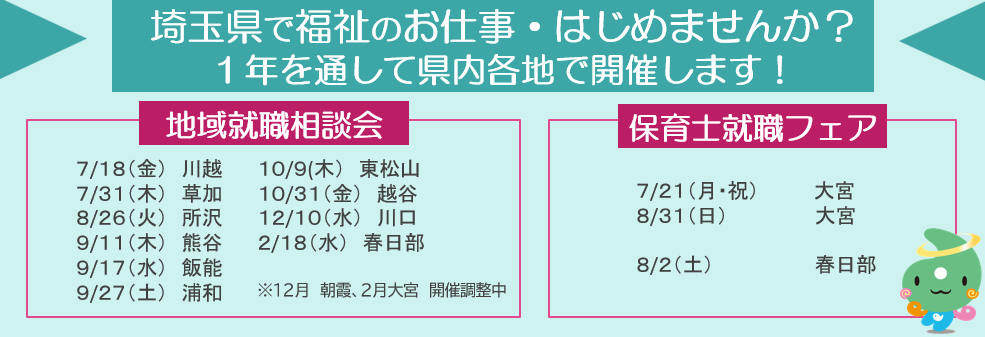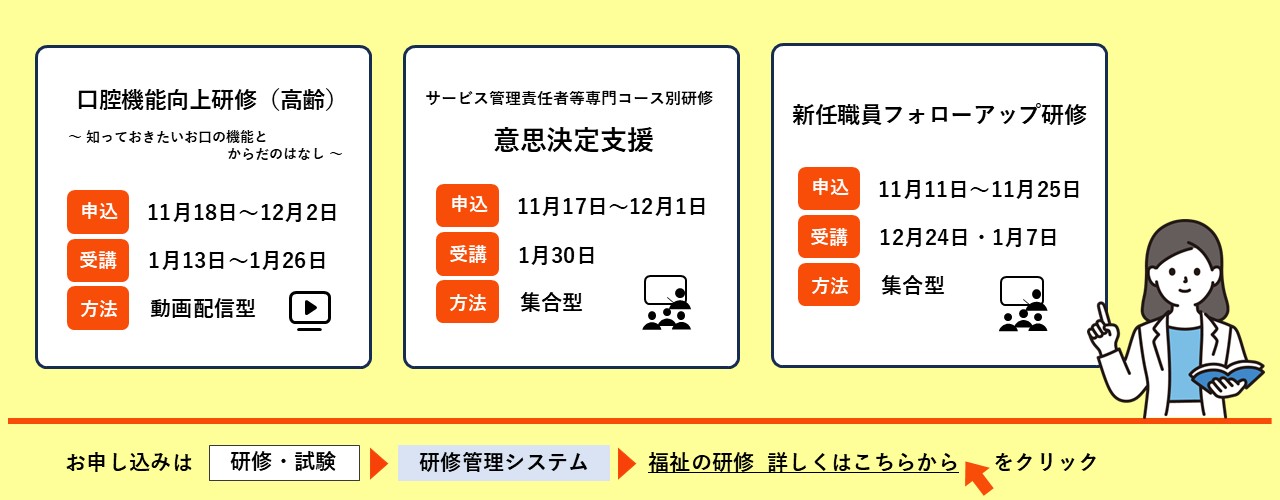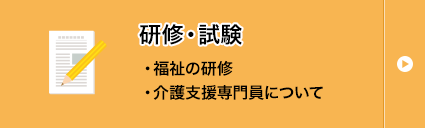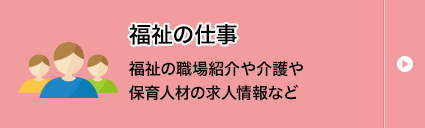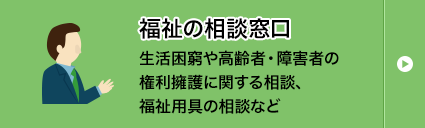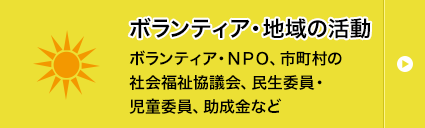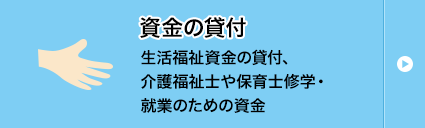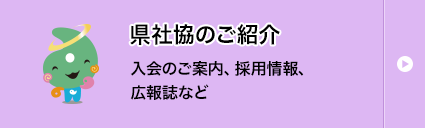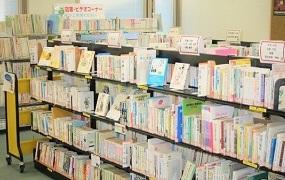県社協のご紹介県社協のご紹介
県内各種別協議会県内各種別協議会
彩の国すこやかプラザ彩の国すこやかプラザ
福祉の相談窓口福祉の相談窓口
入札のご案内入札のご案内
会員向けコーナー会員向けコーナー
- 埼玉県市町村社協連絡会
- R7彩の国ボランティア体験プログラム担当者会議事前アンケート調査結果
- 市町村社協における成年後見関連事業の取組状況
- 市町村社協における市民後見人の活動状況
- ボランティアコーディネーター新任研修
- 社協新任役職員向け動画(社会福祉協議会の理解)
- 市町村社協 常務理事・事務局長及び地域福祉担当課長会議 資料
- 市町村社協 会計関連資料
- 市町村社協 会計決算動画
- 市町村社協 会計初任者動画
- 福祉教育啓発パンフレット「ともに生きる『ふ・く・し』について」
- 災害関連資料
- 市町村社協災害ボランティアセンターモデルマニュアル
- 日常生活自立支援事業
- 生活福祉資金を活用した住民支援
- 生活福祉資金チェックシート・認定調書
- 生活福祉資金等様式集
- 市町村社協組織及び事業の取組状況について
- 発行物
- その他調査結果
ボランティア・地域の活動ボランティア・地域の活動
資金の貸付資金の貸付
- 生活福祉資金貸付金(本則貸付金)のATM返済のお知らせ
- 教育支援資金貸付のご案内
- 生活福祉資金特例貸付における償還免除について(Information on Exemption of Small and Comprehensive Loan)
- Information on Exemption of Small and Comprehensive Loan(For foreigners)
- 令和6年能登半島地震による生活福祉資金の特例貸付について
- 生活福祉資金などの貸付制度
- 介護分野での修学や就職のための支援資金貸付制度
- 保育分野での修学や就職のための支援資金貸付制度
- ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付制度
- ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業(住宅支援資金)
- 児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付制度
- 埼玉県社協生活福祉資金YouTubeチャンネル運用方針
会員用ページ
社協用Copyright(c) 2019 埼玉県社会福祉協議会 福祉情報センターAll Rights Reserved.